公開日: 2025.6.17
紙と属人化からの脱却で「稼ぐ現場」へ。データで語れる現場づくりが成果を生み出す

属人化した紙運用、タイムラグのある情報共有、現場との距離感。これまで製造現場が抱えていた課題に、Smart Craftが変化のきっかけをもたらしました。
導入から半年、三恵技研工業株式会社様の戸田工場(以下「戸田工場」)では「自走する現場」が実現しつつあり、さらに「稼ぐ現場」への一歩を踏み出そうとしています。
本記事では、現場でのリアルな変化と成果、そして次なる挑戦について、工場を支えるキーパーソンたちの声を通してお届けします。
稼ぐ現場とは?副工場長が描く工場の未来像
属人化したアナログ運用からの脱却、現場データのリアルタイム可視化、そして、改善の自走化へ。戸田工場では、Smart Craft導入をきっかけに、従来の製造現場の在り方を大きく見直す取り組みが進んでいます。その背景には、トップダウンではなく「現場が動く仕組みづくり」を重視する大井副工場長の明確なビジョンと、現場に寄り添い続けるSmart Craftの伴走型サポートの存在がありました。
「自走する現場」を通過点に、「稼ぐ現場」をつくる。そう語る大井様に、改革の手応えと今後の展望を伺いました。
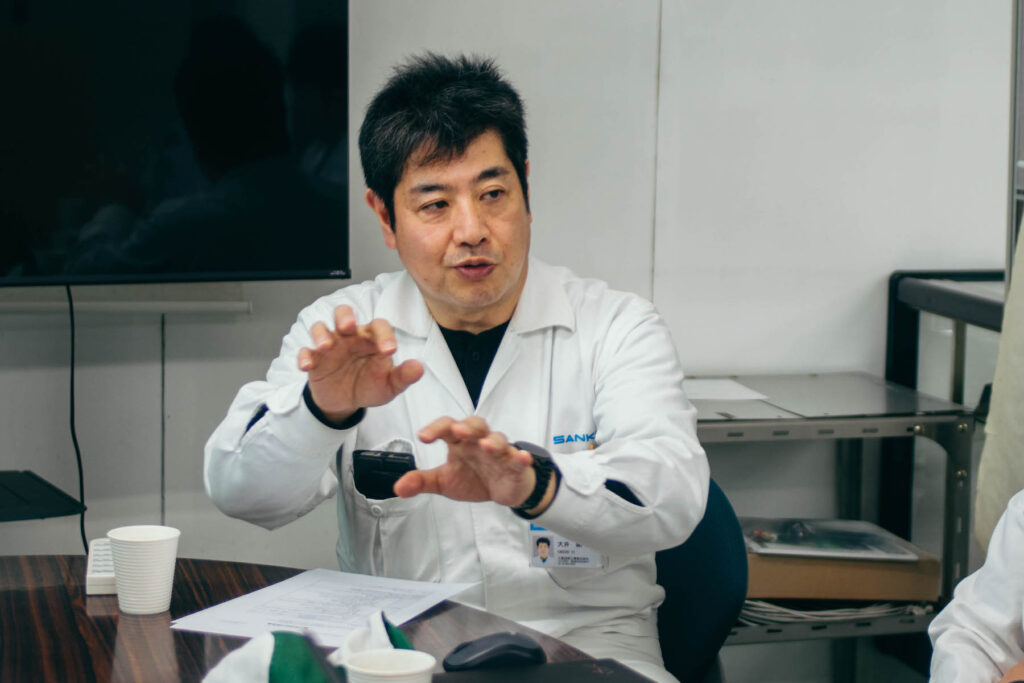
属人化とアナログ運用が抱えていた課題
Smart Craft導入前の戸田工場では、実績を紙に手書きで記録しており、集計にも多くの時間を要していました。情報のタイムラグや精度のばらつきにより、判断に必要なデータがその場にないまま議論が進んでしまうことも少なくありませんでした。
そのため、リアルタイムで実績をデータ化できる仕組みが必要であるという危機感が、ツール選定の出発点となりました。
Smart Craftを選んだ理由:発展途上であることの強み
そうした中で注目したのが、Smart Craftでした。選定の決め手は、「システムが発展途上であった」ことにあります。
完成されたシステムは一見すると理想的に見えるものの、自由度が低く、ユーザーがシステムに合わせて運用せざるを得ないケースも少なくありません。一方、Smart Craftは新機能を隔週でリリースするなど、現場の声をもとに常に進化を続けています。自社のニーズにも柔軟に対応してくれるという期待感があり、さらに、カスタマーサクセス(以下「CS」)担当が伴走してくれる体制にも大きな安心感がありました。
トップダウンではなく、現場主導の推進体制
月に一度、課長以上を対象とした会議体が設けられており、一定の課題は把握できております。しかしながら、現場との公式な対話の機会は限られており、自分がすべてを決めてしまうとトップダウンになってしまうという懸念がありました。そのため、現場が自ら考え、具現化していくための体制づくりに力を注いでいます。
「きっかけを作り、仕組みを整えるのが自分の役割ですが、実際に現場の課題を見つけ、改善を進めていくのは現場自身です。現場が自走する状態をつくることが、本質だと考えています」と語ります。
成果と手応え、そして次のステップへ
Smart Craftによる進捗や実績の見える化は、すでに生産性向上や残業時間の削減といった具体的な成果につながっています。これにより、戸田工場は社内においてDXの成功事例として認識され、他工場からの関心も高まりつつあります。
その背景には、ここ数年で強化された人事評価制度の存在があります。現在では、工場単位での収支が評価対象となり、報酬にも反映される仕組みが整備されています。さらに、3年前から導入された「フィードバック面談」により、上司からの具体的な説明を通じて、自身の業務を見直す文化が根付き始めています。
「生産性が向上すれば、残業が減って楽になります。さらに生産性を上げることで、所定労働時間内により多くの生産が可能となり、結果として売上が伸び、最終的には給与にも反映されます。こうした好循環をつくることが、自分のミッションであり、目指す姿です」と語ります。
今後の展望:現場の「感覚」を「データ」に変える
現在、Smart Craftの活用はプレス工程に限定されていますが、今後は溶接、仕上げ、検査といった他の工程への展開も視野に入れています。目指すのは、受注と同時に納期を即座に回答できる工場の実現です。
現状では、リードタイムを考慮しながらスケジューリングを行っているため、在庫が過剰になったり、逆に不足したりするケースも発生しています。これを防ぐためにも、リアルタイムな製造・出荷計画の可視化が不可欠です。
また、原価管理の高度化も次なるチャレンジとして位置づけています。現在は、どんぶり勘定とまではいかないものの、ある程度まとまった単位での原価把握となっています。理想は受注単位、究極的には一品単位で原価を把握し、あらゆる側面で収支を正確に判断できる状態を実現することです。
こうした経営判断を現場レベルで支える仕組みづくりが、今後のフェーズとなっています。
期待するのは「伴走するシステム」
Smart Craftに対しては、「発展途上だからこそ、自分たちの課題を一緒に考え、それをシステムに反映してくれる」点を最も評価しています。また、追加された機能が現場に定着するよう、CS担当が伴走してくれる体制にも「自社開発では得がたい安心感がある」と語ります。
戸田工場の挑戦は、属人化やアナログ業務からの脱却を経て、「自走する現場」を通過点とし、「稼ぐ現場」をつくることです。 Smart Craftは、その未来像を支える進化し続けるパートナーとして、確かな存在感を放っています。

感覚からデータへ。Smart Craftで実現した「データで語れる現場」
戸田工場では、Smart Craft導入から半年が経過し、Smart Craftを活用した現場改革が着実に進んでいます。紙による記録や属人化した運用から脱却し、リアルタイムで正確な実績データをもとにした改善活動が可能となりました。その背景には、現場の課題に丁寧に向き合いながら、地に足のついた取り組みを続けてきた努力があります。
今回、日々Smart Craftを活用しながら製造現場を支える、池田様(生産課 課長)、皆川様(生産課 係長)、間彦様(生産課 副係長)、堀込様(生産課)に、そのリアルな手応えを伺いました。
アナログ管理からの脱却で、リアルタイムかつ高精度の実績収集を実現
これまでの現場では、生産計画をExcelで作成し、実績は紙に手書きで記録していました。特に繁忙期には、1週間分の記録をまとめて記入することもあり、タイムリーな実績収集が難しく、実績データの精度にも課題がありました。
Smart Craftの導入により、これまでプレス機ごとに掲示していた紙の作業計画はタブレットに置き換えられ、その場での入力が可能になったことで、リアルタイムかつ正確な実績を取得できるようになりました。
現場作業者は、自分が担当する設備の情報だけを簡単に絞り込んで確認できるようになり、次の指示を即座に把握できます。これにより、事前の準備や段取りもスムーズに進められるようになっています。
また、異動してきたばかりの管理者にとっては、計画全体の把握が難しく、業務の引き継ぎにも時間を要していましたが、Smart Craftのガントチャート機能によって計画全体の見える化が進み、短期間で現場を把握できるようになりました。
以前はプレス機の音からおおよその進捗を感じ取っていましたが、現場を離れてしまうと状況を把握するのが困難でした。現在では、スマートフォンやタブレットを通じて、各工程や設備の進捗状況をどこからでもリアルタイムで確認できるようになり、大変助かっています。
さらに、作業の承認通知も即時に共有されるため、情報の行き違いが減少。製造現場の状況が誰の目にも明確に見えるようになったことで、生産計画の立案や調整も、以前より格段に効率的になっています。

多国籍な現場に不可欠な多言語対応と直感的な操作性
現場には外国人実習生も多く、日本語だけでは十分に伝わらない場面もあります。Smart Craftは多言語に対応しており、英語表示への切り替えが可能なことから、紙での運用と比較して、現場作業者からの問い合わせが大幅に減少しました。
「通訳の方でも専門用語が正確に伝わらないことがあるが、Smart Craftであれば正しい意味で画面に表示されるため、確実に意図が伝わる」と間彦様は語ります。
さらに、多言語対応に加えて、画面設計も非常にシンプルかつ直感的であるため、一般的な基幹システムに見られるような複雑な操作は不要で、とても使いやすいといった現場作業者の声も。
漢字の読み書きが苦手な外国人実習生にも配慮し、管理側で登録する文言はできるだけカタカナにするなど、細かな工夫も重ねています。特に漢字の記入が不要になったことで、作業者の負担も軽減。記入ミスや、管理者が確認のために聞き直す手間も減少し、業務効率が向上しています。

「作業の見える化」が現場の姿勢を変える
Smart Craftを導入してから、現場作業者自身が「次に何をすればいいか」を即座に把握できるようになり、受け身の作業から自律的な行動へと変わりつつあります。
「自分がやった作業をちゃんと入力してくれるのを見ると、そこに作業者の意思が感じられる」と話すのは堀込様。
情報が見えるようになったことで、「もっと早く終われば早く帰れる」「作業効率が上がれば生産数も伸ばせる」と、現場でも改善への意識が少しずつ根付き始めています。
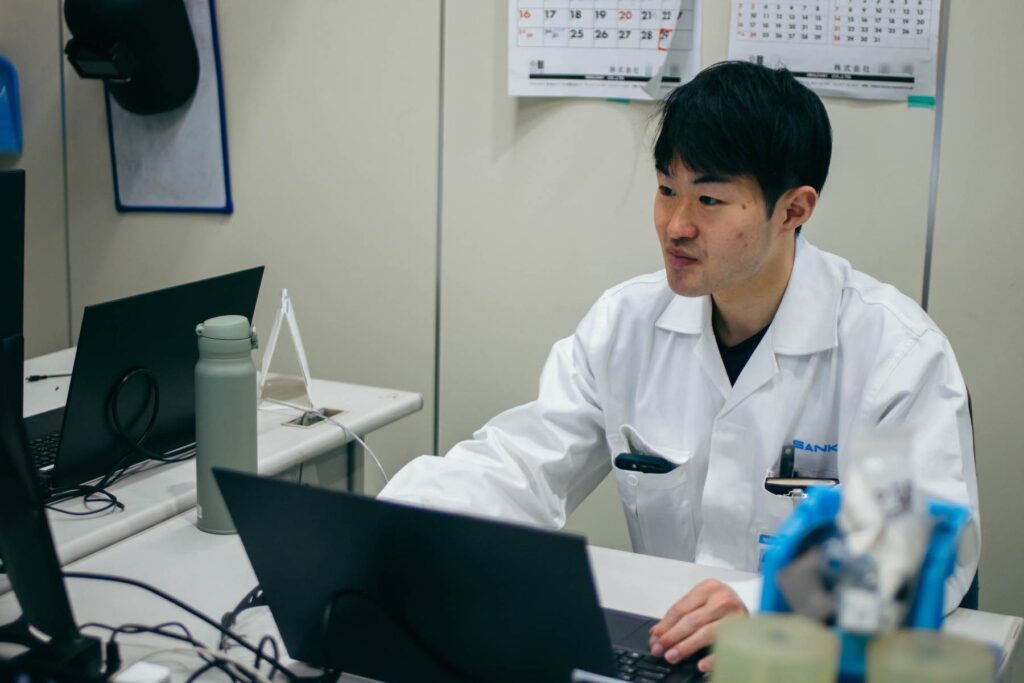
次のステップはデータ活用による改善サイクルの強化
導入から半年が経ち、正確性のあるデータがリアルタイムで取得できる環境が整った今、このデータをいかに改善に結びつけるかが新たな課題となっています。
例えば、Smart Craftによりサイクルタイムを人別に比較することが可能になり、ばらつきが可視化されたことで、平準化や作業改善といった具体的な取り組みが始まっています。
「改善によって現場作業者が残業せず早く帰れるようにしたいし、さらに改善することで所定労働時間内での生産量を増やしていきたい。そうすれば最終的に会社の利益にもつながる」と池田様は語ります。
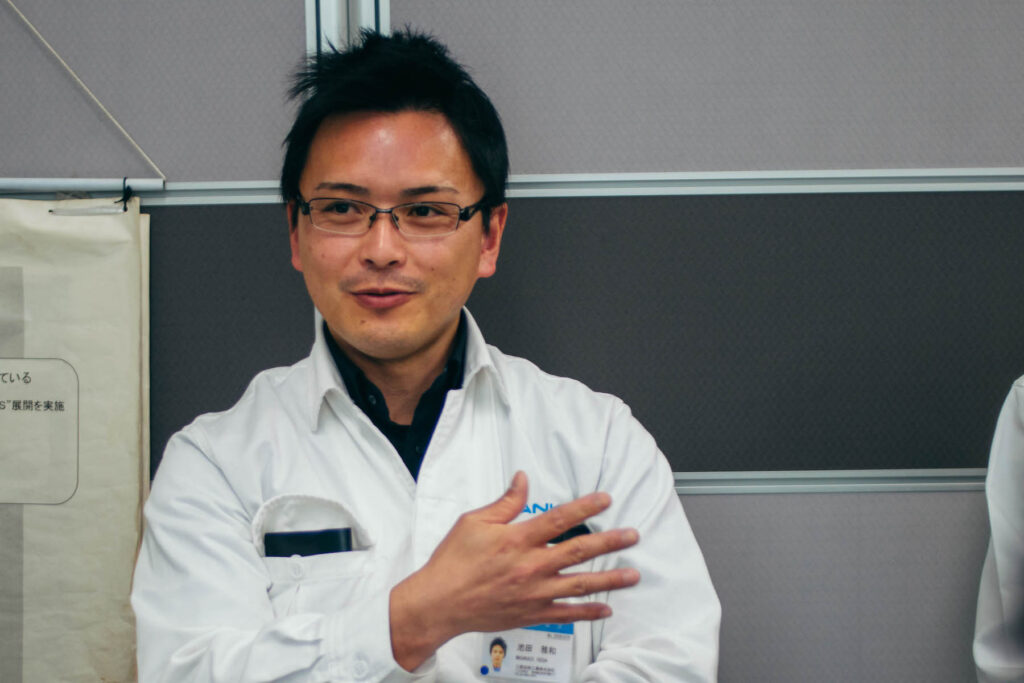
Smart Craft導入を検討している企業へのメッセージ:目標を定め、着実に進めることが達成への近道
Smart Craftの導入を検討している企業の方々にお伝えしたいのは、「目標を定める」ことと「着実に進める」ことです。
戸田工場では「業務効率化」を大きな目標に掲げ、その第一歩として「生産進捗の見える化」と「作業日報のペーパーレス化」の2つに取り組みました。BOP(部品表)の考え方を軸に工程設計を行い、Smart Craft上で生産指示と実績を紐付けることで、進捗の可視化が実現。日々のデータがリアルタイムで上がってくるようになり、着実な手応えを感じていました。
しかし一方で、作業日報の運用はなかなか廃止できず、その理由を探った結果、作業日報に記録されている情報が在庫計上に必要であることが分かりました。そこで、Smart Craftで取得した実績データを在庫管理にも活用できるよう、MRP(資材所要計画)の考え方を取り入れた工程設計へと移行し、マスタの再構築を行いました。これにより、在庫計上・進捗管理・稼働実績収集のすべてがSmart Craft上で完結するようになり、ようやく作業日報を廃止することができました。
多くの時間をかけて設定したマスタを手放すのは大きな決断でしたが、目標が明確だったからこそ、ブレずに決断できました。いきなり完成形を目指すのではなく、小さく始めて、少しずつ積み重ねていくことが大切です。そうした積み上げの結果、安定運用に至り、最終的に目標の達成につながっていきました。
「Smart CraftのCS担当の方が、そうした私たちの歩みに丁寧に寄り添ってくださったから、ここまで来ることができました」と皆川様は語ります。
「できれば他社には導入してほしくないくらいです(笑)。Smart Craftさんが他社対応で忙しくなってしまうと、私たちへのサポートの時間が減ってしまいそうで…(笑)。でも、サービスが終了してしまうのも困るので、やっぱり売れてほしいですね(笑)」と、場を和ませる冗談も交えながら、Smart Craftが現場にしっかりと根づいている様子がうかがえました。
